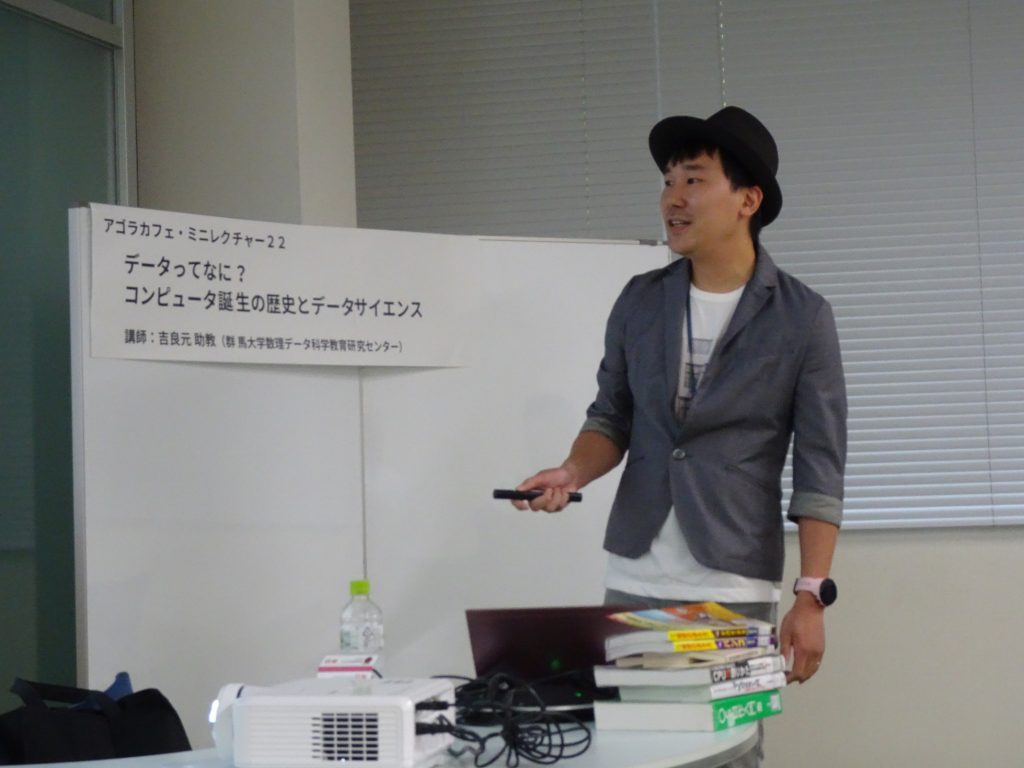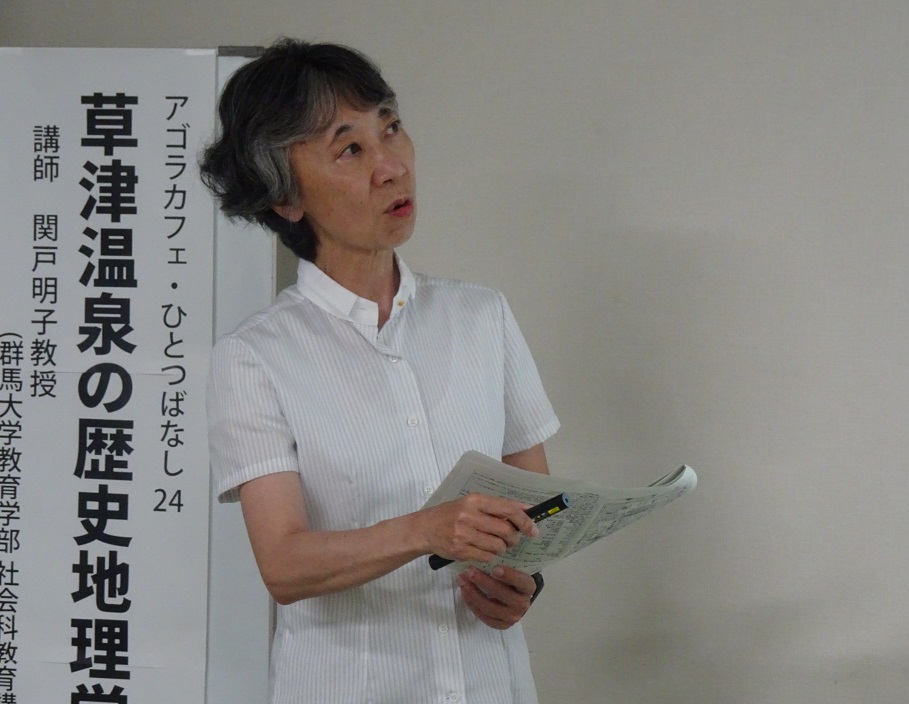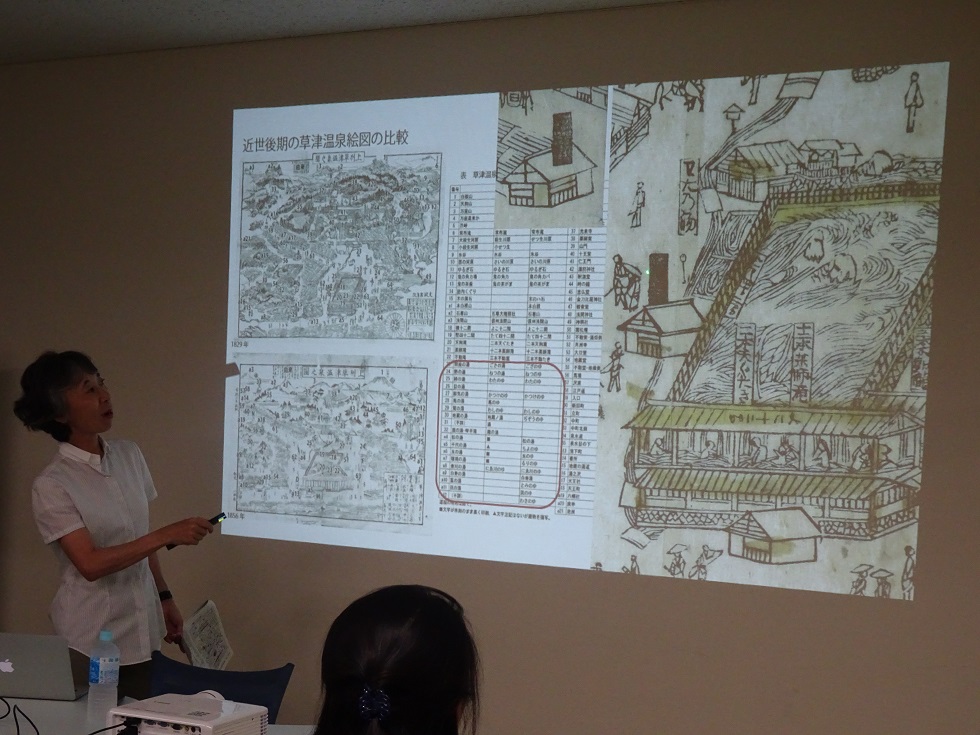こんにちは,中央図書館です。
6月27日(木)16:30から,中央図書館前のウッドデッキにて茶道部と協同でチャリティー納涼茶会を実施しました。前日から雨が心配されましたが,茶道部の学生さんの熱意が通じたのか,無事に開催することができました。
会場では,茶道部の学生さんが涼やかな浴衣姿でお出迎え。お点前を初めて間近で見る方,毎年足を運んでくださる方など様々でしたが, 訪れた方は皆さん和やかな雰囲気の中でお茶とお菓子を楽しんでいました。
今年4年目を迎えたチャリティー茶会は,2016年の熊本地震を契機に,災害被災地支援を目的として毎年実施しています。今回は西日本豪雨の被災地支援として準備してきましたが,直前の 6月16日に新潟・山形地震が発生したため,急遽支援先を変更しての開催となりました。
学生さん,教職員をはじめ,地域の方も足を運んでくださり,寄付だけの方を含め130名の方にご参加いただきました。収益の28,750円は,茶道部の学生さんが 「ふるさとチョイス災害支援」サイトを通じて,新潟県村上市へ寄付しました。 ご参加・ご寄付いただいた皆様,ありがとうございました。 そして,雨を心配しながら準備を進めてきた茶道部の皆さん,天気が味方してくれてよかったですね。お疲れ様でした!

お知らせ:チャリティー納涼茶会について(6/27,8/22更新)
https://www.media.gunma-u.ac.jp/announce/2019/clib/2019061000.html